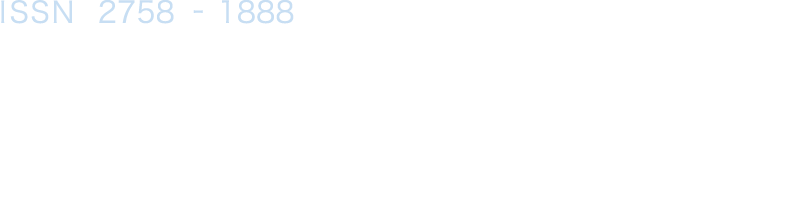核融合科学研究所では、プラズマの中で起こるさまざまな現象を理解し、それを予測・制御する手法を探るために、スーパーコンピュータを活用して理論・シミュレーション研究を行ってきました。2025年7月、この研究をさらに前進させるため、量子科学技術研究開発機構(QST)との共同調達により、新しいスーパーコンピュータ「プラズマシミュレータ」を導入しましたのでこの場をお借りしてご紹介いたします。
私たちが研究している核融合プラズマは正負の電荷を持つ無数の粒子が互いに、そして粒子を閉じ込めるドーナツ型の磁場とも複雑に影響しあって、様々な集団現象や波と粒子の相互作用などが生じている「複雑系」をなしています。またここでは、プラズマと閉じ込め容器との相互作用といったミクロスケールの現象から、半径1m程度のプラズマのスケールまで、大小様々なスケールの現象が絡み合っています。こうした多様な現象を理解するため、私たちは数値計算プログラムを開発し、それを実行するスーパーコンピュータを駆使して研究を進めてきました。このスーパーコンピュータは、国内の大学や研究機関の研究者と共有され、大学共同利用機関としての研究所の重要な役割を担っています。
皆さんも日々実感されているように、コンピュータの性能は目覚ましく進歩しています。今や家庭用パソコンの能力も、かつてのスーパーコンピュータに匹敵するほどです。この進化により、以前は不可能だった大規模で複雑なシミュレーションが可能になり、プラズマの仕組みが一つ一つ明らかになってきました。当研究所でもスーパーコンピュータを5〜6年ごとに更新してきましたが、今回は初めてQSTとの共同で導入・運用することとなりました。新しい「プラズマシミュレータ」は、QST六ヶ所フュージョンエネルギー研究所に設置され、3つの異なる特徴を持つサブシステムで構成されています。
サブシステムA:従来型のCPUを用いたシステムで、総演算性能は5.9ペタフロップス(1ペタフロップスは1秒間に1千兆回の計算が可能)。
サブシステムB:GPU(人工知能やゲームなどで利用される高速演算装置)とCPUを1つのチップに統合した「APU」を搭載し、総演算性能は34.3ペタフロップス。国内の研究機関のスーパーコンピュータへの導入はこれが初めてで、国内外から注目を集めています。
サブシステムC:演算性能は控えめながら大容量メモリを搭載し、大規模データ処理などに適しています。
今回の更新で最も大きな変化は、APUの導入です。近年、CPUの性能向上が限界を迎えつつある中、電力効率に優れたGPUベースのスーパーコンピュータが世界の主流となりつつあります。ただし、GPUは従来のCPUとは仕組みが異なるため、従来のプログラムをそのままでは使えず、大がかりな書き換えが必要でした。APUはこの両者を統合した新しい構造のチップで、既存のCPU向けプログラムを少しずつGPU対応に置き換えていける柔軟性があります。これにより、日本の核融合プラズマシミュレーションもGPU時代へとスムーズに移行できると期待されています。さらに、新しいシステムでは従来のスーパーコンピュータで使われてきたC/C++やFORTRANに加え、PythonやJuliaなど最近のAI分野で活用されるようになってきたプログラム言語にも対応しました。近年、核融合科学分野においてもAIの技法を取り入れたシミュレーションが使われるようになってきており、こうした新技術とのGPUベースの計算機との相性の良さが、核融合科学研究分野にも新しい風を吹きこむものと期待しています。
7月の運用開始時点で、全国から約250名の利用希望者が集まり、その中には多くの大学院生も含まれていました。6月には初の利用者講習会を開催し、今後も新しい計算機に適したプログラミング技術の習得を支援していく予定です。新しい「プラズマシミュレータ」が、全国の共同研究者の研究を支える大きな力となることを心から願っています。
(構造形成・持続性ユニット 准教授、プラズマシミュレータタスクグループ)