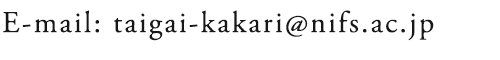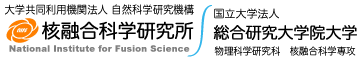HOME > ニュース > プレスリリース > 核融合研究が更に進展
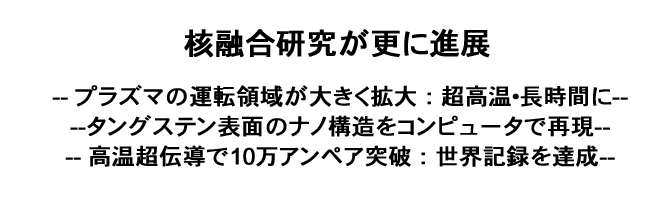
平成26年3月31日
自然科学研究機構 核融合科学研究所(岐阜県土岐市 所長・小森彰夫)では、平成25年度の研究を終了し、上記3つに代表される世界をリードする研究成果を上げ、核融合研究を更に前進させることに成功しました。以下に詳しく説明します。
- 大型ヘリカル装置(LHD)において1億度に迫るイオン温度9,400万度を達成しました。また2,300万度の電子温度を48分間、定常に維持する長時間化にも成功しました。
- ヘリウムが核融合炉内壁候補材料であるタングステンに衝突したとき、表面部分がナノスケールの泡状構造に変形することが実験的に知られていましたが、この現象をコンピュータシミュレーションで再現することに成功しました。この結果、構造形成の物理機構が解明されました。
- 日本で開発された高性能の「イットリウム系」高温超伝導線材を用いることにより、世界的な記録となる10万アンペアの電流値を達成しました。テープ形状である線材を単純かつ強固に重ねて、大型の導体を構成するという新しい技術によるものです。
これらの成果は、4月2日から4日まで核融合科学研究所で行われる「平成25年度研究プロジェクト成果報告会」において発表されます。
報道資料-その1
プラズマの運転領域が大きく拡大:
超高温、長時間に—-
大型ヘリカル装置(LHD)において、
“1億度”に迫る温度を達成
プレスリリース内容
我が国独自のアイデアによる世界最大の超伝導核融合実験装置である大型ヘリカル装置(LHD)では、平成25年10月2日から12月25日にかけて実施した平成 25年度のプラズマ実験の結果、1億度に迫るイオン温度9,400万度を達成しました。この超高温状態の実現とともに、長時間運転の領域も拡大し、2,300万度の電子温度を48分間、定常に維持することにも成功しました。
LHDでは核融合を目指した超高温プラズマの実験研究を進めています。近年、燃料粒子(水素あるいはヘリウム)の制御によりプラズマ性能が向上しプラズマ運転領域が拡大しています。特に、平成25年度の第17サイクルプラズマ実験において、二つの新記録を得ることができました。イオン温度については、昨年度、記録された8,500万度を超える9,400万度を達成しました(図1-1)。この時の密度は1ccあたり10兆個です。また、定常運転については、1,200キロワットの加熱電力によって約48分間のプラズマの保持に成功しました。この定常プラズマに注入された総エネルギー量はこれまでのLHDが持つ世界記録1.6ギガジュールの2倍以上である3.4ギガジュールに達しました(図1-2)。
山田弘司・大型ヘリカル装置計画研究総主幹は「何がプラズマ性能の向上をもたらすかの理解が進み、成果をあげられました。発電実証を行う核融合炉を設計するためには、LHDにおいて核融合で燃えるプラズマを見通せるようになる必要があります。そのために、LHDの最終目標である1億2,000万度のイオン温度を密度1ccあたり20兆個で達成すること、また超高温プラズマの定常運転実証のために3,000キロワットの加熱電力で1時間保持することが必要ですが、その目標に向かって着実に前進することができました」と話しています。
今回の新記録となる研究成果
- LHDにおいて、9,400万度のイオン温度を密度10兆個/ccで達成しました。この高温化のカギは、イオンを加熱する水素ビームをプラズマの中心までより多く届かせ、効率的な加熱が起こるようにしたことです。
プラズマの燃料粒子はプラズマと金属の真空容器内壁との間で再循環し、余剰のガスを発生させます。電磁波を用いて生成したプラズマをあらかじめ容器内壁にあてて、容器内壁から余剰ガスをたたき出しておくことで、本実験のプラズマ生成中に余剰のガスが発生しないよう調整することができました。この結果、水素ビームがプラズマ中心により多く届きイオンの加熱効率を向上させました。 - 長時間の定常運転においても、余剰のガスによってプラズマの密度の制御が阻害されます。燃料粒子供給の制御性能(帰還制御)を改善することにより、今回大幅な運転領域の拡大を実現しました。
これら成果の社会的意義
核融合炉を見通すことができるプラズマへの性能拡大とその理解が進展
LHDの装置仕様(プラズマの大きさ、磁場の強さ、加熱電力など)で、イオン温度1億2,000万度を1ccあたり20兆個の密度で実証し、そのプラズマを詳しく調べることによって、発電実証を行う核融合炉の設計をより確実なものとすることができます。
燃料粒子の制御がプラズマの性能を決めるカギであることの理解が進み、実際その指導原理によってプラズマの性能が拡大できました。これらの成果により、プラズマ性能の最終目標に数字だけでなく、理解としてもより近づいたと言えます。
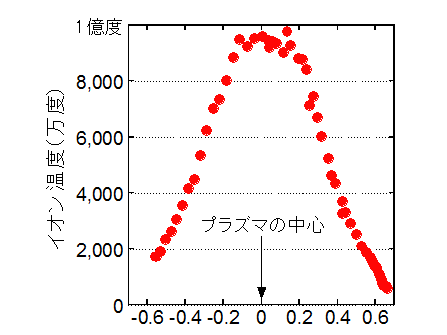 |
|---|
| 図1-1 最高イオン温度9,400万度を記録したプラズマ中のイオン温度分布。 プラズマはおよそ0.6メートルの断面半径を持っていますが、加熱される中心部の温度が最も高くなります。 |
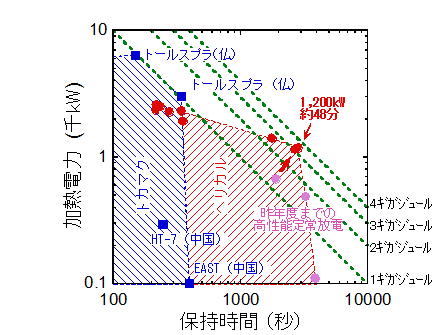 |
| 図1-2 加熱電力と保持時間で見た定常運転達成領域。桃色丸が平成24年度までのデータでLHDはプラズマへの総注入エネルギー(電力×時間)で既に世界一でした。今年度のデータが赤丸であり、これまでの記録を大きく上回ることができました。 |
報道資料-その2
-- タングステン表面のナノ構造をコンピュータで再現-—
ヘリウムの衝突によって誘起されるタングステン表面のナノ構造形成の物理機構を解明
プレスリリース内容
ヘリウムが核融合炉内壁候補材料であるタングステンに衝突したとき、大量のヘリウムがタングステンの中で泡状になる(自己凝集する)ことによって表面部分が発泡スチロール状のナノスケール微細構造に変形することをコンピュータシミュレーションにより再現しました。これは実験研究で観測されている材料表面の泡状化や毛細状ナノスケール微細構造形成の解明につながる成果です。
核融合発電を実現するためには、核融合炉やその周辺装置に用いる材料の開発が重要です。将来の核融合発電時には核融合反応によってヘリウムが発生しますが、実験室の研究で、大量のプラズマ化したヘリウムを、真空容器の内壁表面等の候補材料であるタングステンに当てると、タングステン表面に泡状や毛細状のナノスケールの微細構造が作られる現象が観測されています。これらの微細構造は、材料の耐久性、したがって、内壁表面等の部品の交換頻度に影響すると考えられるため、その理解は、将来の内壁表面等の材料の研究開発に大きく貢献するものと期待されています。
今回、ナノスケール微細構造形成までの過程を、(1)ヘリウムの侵入過程、(2)ヘリウムの拡散・凝集過程、(3)ヘリウムバブルの成長過程、(4)表面微細構造の成長過程の4段階に分け、それぞれの過程の解析に必要とされる4種類のシミュレーションコードの開発・整備を行い、スーパーコンピュータで大規模シミュレーションを実施することにより、大量のヘリウムがタングステンの中で泡状に自己凝集することによって表面部分がナノスケールの泡状構造に変形する複雑な物理過程を再現することに世界で初めて成功しました(図2-1および2)。
堀内利得・数値実験研究プロジェクト研究総主幹は「ヘリウムプラズマの衝突を受けて発現するタングステン表面の微細構造形成の解明に取り組み、大量のヘリウムがタングステンの中で泡状に自己凝集することによって表面部分がナノスケールの泡状構造に変形することをコンピュータシミュレーションにより再現しました。今回の研究成果は、実験で観測されているタングステンのナノスケール微細構造の形成メカニズム解明につながるものと考えられます」と話しています。
新しい研究成果
- 将来の核融合発電時には核融合反応によってヘリウムが発生します。真空容器の内壁材料候補であるタングステンが、高温プラズマ化した大量のヘリウムに晒されると、その表面にヘリウムの発泡現象が現れることが実験で分かっていましたが、今回コンピュータシミュレーションにより世界で初めて再現しました。
- この結果により、ヘリウムがタングステン内部で高い拡散速度と自己凝集能力を持っていることが、泡状構造への成長の原因であることが分かりました。
これら成果の社会的意義
核融合炉内壁候補材料の研究が進展
- 核融合炉で発生するヘリウムが、真空容器の内壁表面の構造変化をもたらす原因となるメカニズムを解明しました。この理解は材料劣化を防止することにつながります。すなわち、より長寿命の真空容器内壁材料の研究開発に大きく貢献することになります。
- 本研究で対象としたナノスケール微細構造は、光触媒や反射防止膜などへの産業応用が期待されており、今回コンピュータシミュレーションでその成長の物理機構が明らかになったことで、プラズマを利用した新しい金属ナノ材料開発法の確立に向けた研究が進みます。
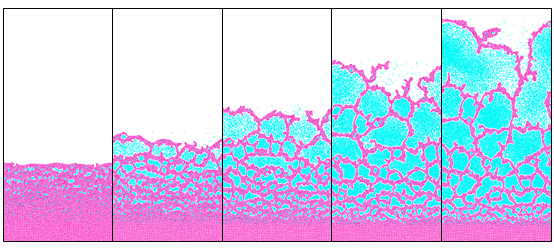 |
|---|
| 図2-1 プラズマを閉じ込める真空容器の内壁候補材料であるタングステンの表面がヘリウムプラズマの衝突を受けて構造変化していく様子をコンピュータシミュレーションで再現したものです。紫色の点がタングステン原子を、水色の点がヘリウム原子を表しています。図の左から右に移るに従って時間が経過する様子を示しています。時間経過と共にタングステン材料内部に徐々にヘリウムが増えていきますが、その際にヘリウムが自己凝集を起こす(泡を作る)ことでこのような表面成長が起こります。 |
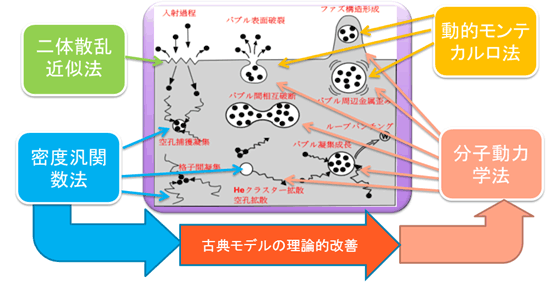 |
| 図2-2 ヘリウム衝突によって誘起されるタングステン表面および内部の各種現象と、それを解明するための各種シミュレーション手法。(1)ヘリウムの侵入過程、(2)ヘリウムの拡散・凝集過程、(3)ヘリウムバブルの成長過程、(4)表面微細構造の成長過程の四段階の過程に合わせて詳細な量子力学的計算(密度汎関数法)や大規模原子集団の為の古典力学的計算(分子動力学法)などを適宜適用し解析しました。また、詳細な量子力学計算を基にして古典力学モデルの理論的改善にも努め、シミュレーションコードの再現性の向上にも努めました。 |
報道資料-その3
-- 高温超伝導で10万アンペア突破:世界記録を達成--
高性能の「イットリウム系」高温超伝導線材を、新しい技術を用いて大型導体化することにより、世界をリードする大電流値を達成
プレスリリース内容
将来の核融合炉のマグネットに適用可能な大電流の「高温超伝導」導体の開発研究を進めた結果、マグネット製作の上限となる超伝導体断面積以下で、世界で類の無い10万アンペアの通電に成功しました。この結果は、日本で開発された高性能の「イットリウム系」高温超伝導線材を用い、東北大学との共同研究によって開発された低抵抗の接続技術を応用することで得られたもので、高温超伝導体を用いた大型マグネットの製作を飛躍的に簡素化できることを提唱しています。
核融合科学研究所の核融合工学研究プロジェクトで設計を進めているヘリカル型核融合炉では、大型・大電流の超伝導導体をドーナツの周りにらせん状に巻いて、直径30メートルを超える巨大なマグネットである「ヘリカルコイル」を製作する必要があります。この核融合炉に必要とされる導体の電流値は、マグネット製作の上限となる超伝導体断面積以下で、10万アンペアという大きなものです。核融合炉では従来の「低温」超伝導導体に代わる安定で経済的な「高温」超伝導導体の導入が期待されていますが、複雑な形状のコイル製作方法に難点がありました。
核融合科学研究所では、高温超伝導コイルの製作法として積層法を提案しており、今回、日本で開発された高性能の「イットリウム系」高温超伝導線材を積層して機械強度に優れた導体を試作しました(図3−1)。その結果、導体の特性試験において到達した電流値は、絶対温度20度(摂氏マイナス253度)で10万アンペアに達し、世界をリードする成果を挙げました(図3−2)。また、東北大学との共同研究により、優れた導体接続技術も開発できました。
相良明男 核融合工学研究プロジェクト研究総主幹は、「核融合マグネットをターゲットとした高温超伝導導体の開発は世界でもまだ始まったばかりですが、通電電流10万アンペアを達成したことに加え、優れた接続技術も開発できたことで、将来のヘリカル型核融合炉の実現に向けて大きな進展となりました」と話しています。
今回の新記録となる研究成果
- 高温超伝導線材を用いた核融合炉マグネット用大電流導体を世界に先駆けて開発し、マグネット製作の上限となる超伝導体断面積以下で、電流10万アンペアを達成しました。これは、世界で独走する成果であり、国際熱核融合実験炉ITERに用いられる導体の性能をも凌駕しています。
- 高温超伝導導体の低抵抗接続技術を開発しました。これにより、核融合炉用の大型マグネットを迅速に製作することが可能となります。
研究成果の社会的意義
高温超伝導体を用いた大型装置の製作が可能に。
- LHDで得られている優れたプラズマ閉じ込め実験の成果をもとに設計を進めているヘリカル型核融合炉について、その工学的実現性を飛躍的に高めます。
- 現在精力的に開発が進められている産業用の高温超伝導機器の製造方法にもインパクトを与え、これらの実用化を加速します。
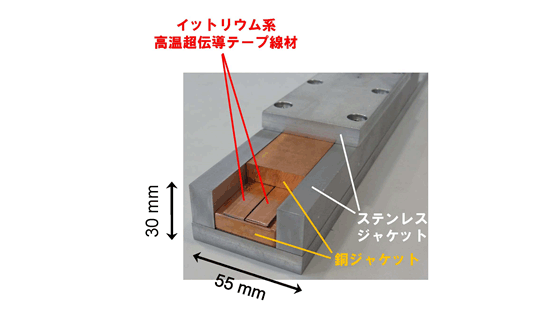 |
|---|
| 図3−1 大電流・高温超伝導導体サンプルの断面写真。一枚あたりの幅10 mm、厚さ0.2 mmのイットリウム系高温超伝導テープ線材を全54枚用いており、電流はこの部分のみに流れます。強度と柔軟性に優れたこのタイプのテープ線材を隙間なく積層するとともに、これらの周りを銅ジャケットとステンレスジャケットで囲むことで、機械的に極めて強固な導体に仕上げています。 |
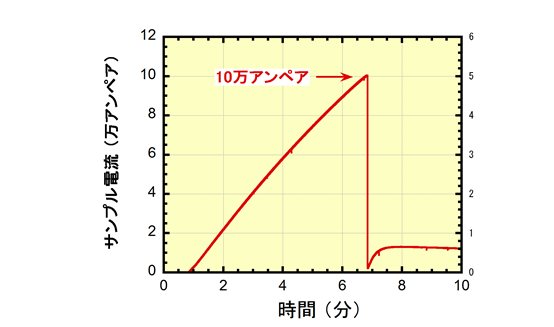 |
| 図3−2 大電流・高温超伝導導体サンプルの特性試験において測定された電流値の時間変化。絶対温度20度(摂氏マイナス253度)において、最大10万アンペアに到達しました。 |
【解説 1】
将来の核融合炉では、その炉心は、密度100兆個/cc以上でイオン温度と電子温度が1億2,000万度を超える超高温のプラズマ状態にあります。この密度は大気の20万分の1程度であることから分かるように、非常に希薄なガス状態でもあります。
このような超高温にまでプラズマを加熱するために、高速の原子ビームや、プラズマ中のイオンあるいは電子と共鳴する電磁波を用います。これらの手法は、それぞれイオンを加熱することが得意なものと、電子を加熱することが得意なものとに分かれます。LHDでは複数の加熱手法を用いて、イオン温度と電子温度がそれぞれ1億2,000万度のプラズマを密度20兆個/ccで実現することを最終目標としています。LHDの装置規模において、この最終目標を達成することが、将来の核融合炉の炉心プラズマを見通すことにつながります。
LHDでは3年前に、FM周波数帯の電磁波(電波)を用いてヘリウムのプラズマを点けると壁に吸着されていた水素がはき出され(壁が洗浄され)、その後に水素でプラズマを点けるとプラズマ周辺部の密度が下がり、高速の原子ビームがプラズマ中心を加熱する効果が上がって高いイオン温度が得られることを発見しました。この手法による燃料粒子(水素あるいはヘリウム)の制御により、加熱効果の向上を図ってきました。図1-3に温度の進展を示します。昨年度に比較して、プラズマ中心部の加熱効率を約16%改善することに成功し、イオン温度を増加させることができました。この加熱効率の評価では、京都大学の二つのグループによる、各々、粒子ビームによるプラズマ加熱の精密な理論計算とプラズマ中の燃料原子密度計測の研究成果が極めて大きな貢献をしました。
LHDが採用しているヘリカル方式は我が国独自のアイデアに基づき、外部の電磁石のみでプラズマを閉じ込めることができることから本質的に定常運転に優れた概念です。この特長を活かして、LHDでは世界最高の定常プラズマ保持実験を進めています。ここでも、加熱電力と燃料粒子の制御が鍵であり、平成25年度の第17サイクル実験では、ヘリウムと水素ガスの注入制御を高度化し、高速で緻密な制御を可能としました。これにより、運転範囲をより高い加熱電力、ついてはより高いプラズマ密度でより長い時間へと拡大することができました。
表1にLHDのプラズマ性能の達成値と最終目標値を核融合条件と並べて示します。赤字が平成25年度の第17サイクル実験で新たに得られた記録です。これらのプラズマ性能の拡大と、そこで得られた物理の理解の深まりはお互いを加速しあっています。平成26年10月には2年に一度の国際原子力機関(IAEA)主催の核融合エネルギー会議があり、そこではLHD実験から25件の論文発表を予定しています。この件数は世界的に秀でた貢献を示しています。
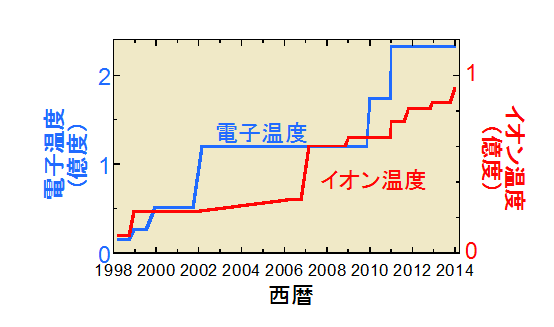 |
|---|
| 図1-3 イオン温度と電子温度の進展。 |
表1 LHDのプラズマ性能。赤字は平成25年度に達成されたものを示します。
| プラズマ性能 | LHD達成値 | LHD最終目標値 | 核融合条件の目安 |
|---|---|---|---|
| イオン温度 | 9,400万度 (密度10兆個/cc) |
1億2,000万度 (密度20兆個/cc) |
1億2,000万度
100兆個/cc 5%(磁場5テスラ) 定常(1年) |
| 電子温度 | 2億3,000万度 (密度2兆個/cc) 1億5,000万度 (密度10兆個/cc) |
1億2,000万度
(密度20兆個/cc) |
|
| 密度 | 1,200兆個/cc
(温度300万度) |
400兆個/cc
(1,500万度) |
|
| ベータ値
(プラズマ圧力/磁場圧力) |
5.1%
(磁場0.425テスラ) 3.7% |
5% (磁場1-2テスラ) |
|
| 定常運転 | 54分 (500kW) 48分
|
1時間(3,000kW) |
【解説 2】
高密度のプラズマを閉じ込める核融合炉の内壁等の表面は常にプラズマに晒されているため、核融合発電を実現するためには、核融合炉壁やその周辺装置に用いる材料の開発が重要です。
核融合炉では水素同位体同士の融合反応によってヘリウムが発生します。ヘリウムの衝突による真空容器の耐久性を調べる実験研究から、内壁表面等の候補材料の1つであるタングステン材料の表面にはヘリウムの衝突によってナノスケールの泡(ヘリウムバブル)が大量に発生するという現象が知られていました。さらに、名古屋大学における実験により2006年には、ヘリウムバブル発生後にもプラズマ照射を続けることで、毛細状のナノスケール微細構造がタングステン表面から生えることが発見されました。タングステンの様に非常に硬い金属においてこの様に表面形状がナノスケールで変化することは全く想像外の現象です。
2009年に数値実験研究プロジェクトの中に、プラズマ壁相互作用の研究を推進するグループを立ち上げ、高温プラズマに晒された核融合炉の真空容器の内壁表面等の候補材料の構造変化や物理特性に関する様々な研究を進めてきました。タングステンの表面および内部におけるヘリウムの挙動の解明の研究では、ナノスケール微細構造形成までの過程を、(1)ヘリウムの侵入過程、(2)ヘリウムの拡散・凝集過程、(3)ヘリウムバブルの成長過程、(4)表面微細構造の成長過程の4段階に分け、それぞれの過程の解析に必要とされる4種類のシミュレーションコードの開発・整備を行いました(図2-2)。さらに、これら開発されたシミュレーションコードを最適に使い分け、スーパーコンピュータで大規模シミュレーションを実施することにより、大量のヘリウムがタングステンの内部で泡状に自己凝集することによって表面部分のタングステンがナノスケールの泡状構造に変形する複雑な物理過程を再現することに成功しました。
この成果は、将来の核融合炉で発生するヘリウムが真空容器の内壁表面等の材料で起こす現象のメカニズム解明と、同材料の研究開発に大きく貢献するものです。すなわち、将来の核融合炉において懸念されるヘリウムによる内壁材料の表面構造変化の原因となるメカニズムの解明、さらには、理解の進展による材料劣化の防止策の開発につながる大きな前進であると考えられます。また、本研究の対象としたナノスケール微細構造は光触媒や反射防止膜などへの産業応用が期待されており、本研究がその物理機構を明らかにしたことで、プラズマを利用した新しい金属ナノ材料開発の促進に貢献するものと考えられます。ここでの研究成果は、本年4月4日に成果報告会の中で発表される他、平成26年10月に行われる国際原子力機関(IAEA)主催の核融合エネルギー会議で発表される予定です。
【解説 3】
核融合科学研究所で設計を進めているヘリカル型核融合炉では、大型・大電流の超伝導導体をドーナツの周りにらせん状に巻いて、直径30メートルを超える巨大な「ヘリカルコイル」を製作する必要があります。この核融合炉に必要とされる導体の電流値は10万アンペアという大きなもので、ちょうどカミナリの電流と同程度です。これを数百本用いてヘリカルコイルを迅速に製作するため、らせんの半周ごとに導体を接続しながら巻線する方法を提案しています(図3−3)。これを可能とするのが、「高温超伝導導体」です。
現在稼働中のLHDやフランスで建設中のITERでは、「低温」超伝導導体が用いられ、液体ヘリウムによって運転温度を絶対温度4度(摂氏マイナス269度)に保ちます。これに対して、「高温」超伝導導体を用いると、運転温度を絶対温度20度(摂氏マイナス253度)以上とすることが可能となり、格段に高い安定性や経済性が得られます。また、液体ヘリウムを大量に使う必要がなく、低温のヘリウムガスだけで十分なため、ヘリウム資源を格段に節約することができます。
今回、核融合科学研究所の柳 長門准教授、相良明男教授と東北大学 量子エネルギー工学専攻の伊藤悟助教、橋爪秀利教授らのチームは、日本で開発された高性能の「イットリウム系」高温超伝導線材を積層して機械強度に優れた導体を製作しました。これを用いてレーストラック型のコイルサンプルを製作し、外部磁場を変化させることで電磁誘導方式によって電流を流しました(図3−4)。その結果、絶対温度20度において最大電流10万アンペアまで到達しました。これは、高温超伝導導体として世界をリードする成果であるとともに、ITERに実際に用いられる低温超伝導導体(電流値6万8千アンペア)をも凌駕する性能です。併せて、導体の一部に新しく開発した「接続技術」を適用したところ、測定された接続抵抗は核融合炉に適用可能な十分低い値となることが実証されました。
この実験に用いたイットリウム系高温超伝導線材は、日本において長年に渡って研究開発され、世界最高の性能を誇るものです。現在、超伝導送電ケーブルや超伝導変圧器、超伝導電力貯蔵装置などスマートグリッドの一端を担う電力機器をはじめ、超伝導リニアモーターカー、超伝導大型モーター、超伝導MRIや超伝導医療用加速器などへの応用が期待されています。今回得られた成果は、これら産業機器用の高温超伝導コイルを製造する上でも革新的な技術を与えるものです。
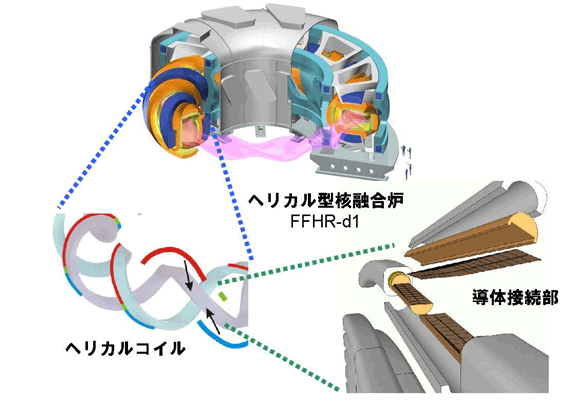 |
|---|
| 図3−3 高温超伝導導体を用いたヘリカルコイル型核融合炉の接続方式巻線の概念図。 |
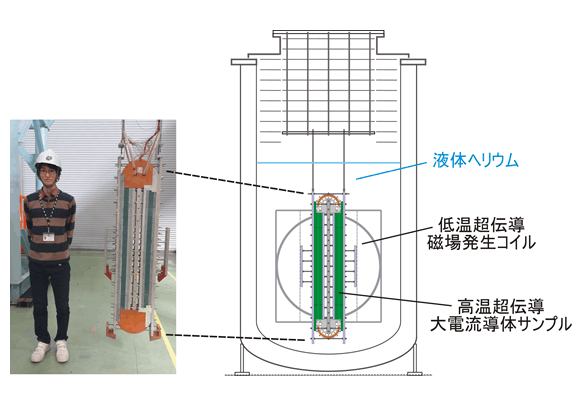 |
| 図3−4 大電流・高温超伝導導体サンプルの全体写真(左)と核融合科学研究所・超伝導マグネット研究棟の大型導体試験設備への装着の様子を示した模式図(右)。 |
【本件のお問い合せ先】
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所
管理部 総務企画課 対外協力係