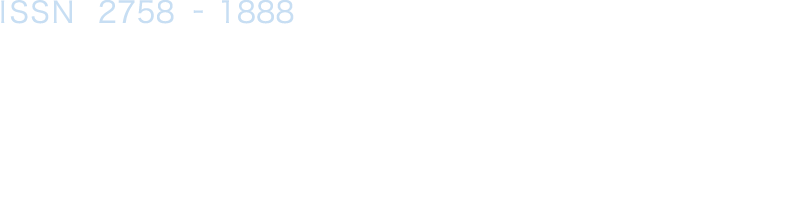2023年 新年のご挨拶「幸せのために」
|
|

|
新しい年の始まりにあたり、幸福ということについて考えたいと思います。
幸せとは何かというテーマは、幅広く、かつ奥深いので、この限られた紙幅と新年挨拶という特別な場は、勝手な自説を展開するには適しません。そこで、一つの文献を手引きにして、その解題のようなスタイルで意見を述べ、皆さんと一緒に考えるきっかけにしたいと思います。文献は、バートランド・ラッセルの『幸福論』(訳:安藤貞雄、岩波文庫、1991; Bertrand Russell, The Conquest of Happiness)です。有名な本ですから、読まれた人も多いと思います。
著者のラッセル(1872--1970)は、ケンブリッジのトリニティーカレッジを出た数学者ですが、彼を有名にしたのは、哲学に関するいささか無邪気な言論でした。「人道的理想や思想の自由を尊重する、彼の多様で顕著な著作群を表彰して」1950年にノーベル文学賞を受けています。加えて、ヴィトゲンシュタイン、アインシュタイン、サルトルなどの有名人との交流が彼の経歴に花を添えています。その自由奔放な人生を可能にしたのは、伯爵家の御曹司という英国貴族としての出自に負うところが大きいと思われます。このように経歴を紹介すると、そんな特別な人の「幸福論」は雲の上のものだと思う人もあるかもしれません。しかし、彼の私生活(結婚・離婚の繰り返し、それらに伴う愛憎や係争など)は、私たち普通の人間から見ると、波乱万丈と表現すべきか、無軌道と言うべきか、どう考えても「幸福」とは思えません。こういう場合、私たちには二つの選択肢があります。そんな「実効性がない幸福論」など御免だとして無視するか、逆にそういう人生でも自分では幸福だと思える「極めて高度な幸福論」として拝聴するか、そのいずれかです。ここでは後者に賭けて、彼の言うことに耳を傾けてみましょう。
著者は数学者らしく、章立てを見れば言わんとするところがおよそ分かるように簡潔な構成をとっています:
- 第一部 不幸の原因
- 1. 何が人びとを不幸にするのか、2. バイロン風の不幸、3. 競争、4. 退屈と興奮、5. 疲れ、6. ねたみ、7. 罪の意識、8. 被害妄想、9. 世評に対するおびえ
- 第二部 幸福をもたらすもの
- 10. 幸福はそれでも可能か、11. 熱意、12. 愛情、13. 家族、14. 仕事、15. 私心のない興味、16. 努力とあきらめ、17. 幸福な人
具体的にどのようなことを述べているのか、少し引用してみましょう。第2章の「バイロン風の不幸」で取り上げられたバイロンとは、これまた放埓な人生を送った詩人ジョージ・ゴードン・バイロン卿(1788--1824)のことです。自分のことを棚に上げてバイロンを不幸者の第一例にするのは、いかがなものかと思ってしまいますが、ラッセルがバイロンに不幸を見るのは、その無軌道な恋愛遍歴についてではありません。
- ”昔の時代に熱心に信奉されていたものの正体をことごとく見抜いてしまって、もはや、なんの生きがいもなくなったことに気づいている ・・(中略)・・ こういう考えをいだいている人びとは、本当に不幸である。”
第6章では「ねたみ」を取り上げています。これは誰しも気を付けなくてはならない普遍的な不幸の原因です。
- ”ねたみの唯一の治療薬は幸福である。しかも、困ったことに、ねたみ自体が幸福への大変な障害になってるのだ。”
このような構図でこの本の章立てを眺めると、ラッセル幸福論の骨組みが分かってきます。「不幸の原因」に挙げていることを総括すると「自分の内部に向かう意識のベクトル」だと言えます。逆に「幸福をもたらすもの」は「外の世界へ向かう意識のベクトル」です。
フロイトによると、自我とは、エス(Es)と呼ばれる内的で生理的な精神世界(意識によって統合されていない無意識的な世界)と、外的な現実世界との狭間で、内側と外側の矛盾を解消すべく喘いでいる、薄くて壊れやすい境界なのだそうです。エスは快感原則が支配する膨大な内部領域(実は精神活動のほとんど全て)であり、エスから意識へと浮き上がってくる「夢」は全て、現実原則に縛られない、快感へ向かう表象だと言います。でも「悪夢」は不快感へ向かっているではないかと反論したくなります。私も年に何度かは「歴史の試験を受けなくてはならなくなったけど、授業に出た記憶がないし、教科書もどこにやったか分からない」という悪夢を見ます。しかしフロイトはこのような夢を次のように解釈します。「でも結局は何とかなって、あなたは無事に暮らしてきた。それが夢の中であなたが求めている快感なのだ。」にわかには信じがたいけれど(エスで起きていることなど、あなたは知らなくてよいのです、とフロイトは言っています)、たしかに悪夢から覚めて現実に戻った時、不幸になったことはないように思います(汗をかいて疲れはしますが)。逆に、心地良い夢も私たちを幸福にすることはありません。自我をストレスから解放する「幸福のための戦略」は、精神の内部(エスの快感原則)を偏重しないこと、外界の現実に関心を向けることです。
このような精神分析の理論に目配せしながら第二部を読んでみましょう。第10章では次のような幸福の分類をしています。
- ”幸福には二種類ある。・・(中略)・・ 動物的なものと精神的なもの、感情的なものと知的なもの、といったふうに区別できるかもしれない。”
- ”あなたの興味をできるかぎり幅広くせよ。そして、あなたの興味を惹く人や物に対する反応を敵意あるものでなく、できるだけ友好的なものにせよ。”
*****
これまで見てきた幸福論から、私たちの未来に向けた示唆を幾つか引き出したいと思います。個人のレベルでも、社会の様々な共同体のレベルでも、究極的な目的は「幸せ」であるべきです。その目指すべき幸福は、とくに共同体においては、ラッセルが分類するところの「知的な幸福」でなくてはなりません。幸福を得るために、知的関心を幅広く外の世界へ向けること。けっして精神的な、内在化した価値(現実世界と乖離したイデオロギー)へ意識を縮退させてはいけません。
私たちは、核融合科学の学際化を旗印にして未来を開こうとしています。あらゆる分野へ積極的に関心を向け、友好的な関係を築いていければ、幸せが得られるはずです。
(核融合科学研究所 所長 吉田善章)