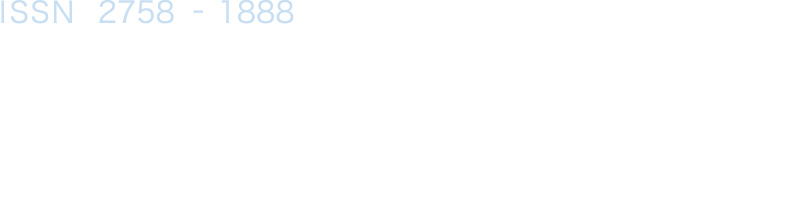明けましておめでとうございます。
所長として新年のあいさつを書くのは3回目になります。「世界はこのようであってほしい」という思いを新年の寿ぎ(ことほぎ)として、一昨年は「未来への勇気と想像力」について、昨年は「幸せのために」と題した所感を述べました。今年は「リスペクト respect」について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
respect を「尊敬」と訳して admire と同義のように考えると、仰ぎ見るような印象が生じますが、語源は「振り返って(re-)見る(spect)」であり、つまり「注意の眼差しを向ける」というのが本来の意味です。「尊重」と訳した方が幾分適切ですが、私が言いたいのは語源どおりの意味です。ぴったりの訳語がないので、リスペクトと言うことにします。
リスペクトがあってはじめて「共感」が生まれます。自分を相手の中に写してみる、あるいは、相手を自分の中に写してみる、このような心の働きが「共感」という現象を生じます。紛争地で家族を亡くし故郷を追われる人々の報道にふれるとき、そういう立場に置かれた人の悲しみ苦しみを想像する。もし自分がそのような立場だったら、どう感じ、どう行動するだろうかと考えてみる。このように共感という感情は、厳しい状況にある「同胞」を思うときに強く巻き起こります。おそらく、人類が集団で生きるなかで育まれてきた生命のメカニズムなのでしょう。これは、自分と他者との同質性あるいは対称性を仮想することによって成り立つ心の現象です。その根本に他者へのリスペクトがあります。そのまま通り過ぎるわけにはいかない、振り返らざるを得ない、そういう他者への関心から生じる感情なのです。
人間の想像力はさらに豊かで、動物や植物、さらには無機的な物の「心」になることもできます。痩せ地で一生懸命に花を咲かせる野草に生きる力をもらう。冬空でまたたく星の孤独さを思う。私たちの言語(認識の世界)は、意味するもの signifiant(すなわち記号)と意味されるもの signifié(すなわち内容)が結びついて成立する意味表象 représentationによって構成されています。たとえば、昴(すばる)という文字は、冬空に懸かるおうし座のプレアデス星団を指す記号であり、その青白い光をイメージさせるわけですが、さらにその天体自体をはみ出た様々な意味が引き寄せられてきます。清少納言が語ったこと、谷村新司が歌ったこと、プレアデス7人姉妹にまつわるギリシャ神話・・・ 語とそれが表す対象が一対一に結びついた「昴」という意味表象が、さらに「記号」となって、様々な意味内容を引き寄せる。このような階層的な現象をロラン・バルトは「神話作用」と呼んでいます。なぜそう名付けたかというと、あまねく神話は、そのような「階層構造」をもっている「超言語」だからです。いろいろな「国造り」の神話は、王権の正統性を印象付ける記号として作用する。獣との交流を語る神話は、部族のアイデンティティやタブーを想起させる記号=トーテムとして作用する(クロード・レヴィ=ストゥルース『悲しき熱帯 Tristes tropiques』)といった具合です。
このような観点から、バルトは「神話」に危険性(とりわけ意識の内部へ向けた権力の介入)を指摘します。いわゆる神話におけるリスペクトは、国家とか民族という構造化された対象(あるいは構造を象徴する英雄)に向けられる「尊敬」であり、まさしく仰ぎ見ることを意味します。人と構造との「非対称性」が「神話」の本質です。「安全神話」「成長神話」などの罪が問われていますが、これらに通底するのは人間性の疎外です。科学も技術も多くの「神話」を生み出し、ばらまいているのではないか?それらが語る夢の裏側で、巧みに美化された欲望がうごめいてはいないか?このことに反省すべき点が多くあると思います。
皮肉なことに、バルトの著書『神話作用 Mythologies』はコマーシャル業界で必読の書になっているという話を聞いたことがあります。できるだけ多くの人にお仕着せの均一な共感を生み出すこと、これが宣伝(プロパガンダ)の目的であり、そのために創作される記号が「神話」なのです。上記の本には、記号化=神話化されたアインシュタインも登場します。アインシュタイン神話を宣伝に利用する業界のなんと多いことか。私たちの分野でも、 E = mc2 という「記号」をあしらった宣伝を目にします。「地上の太陽」という宣伝文句も、核融合を「神話」にしようとする企てであるかのようです。宣伝することが全ていけないと言っているわけではありません。問題は、その目的が何かということです。神話作用が引き寄せようとしている意味内容signifiéが虚構だったりしないかということです。
バルトは「神話」の対極に「詩」を置いていますが、私はそこに「学術」を等置したいと思います。これらが目指すのは、表象を解体し、表象に同化しているものたちの意味を問い直すこと、新しい意味を発見することです。表象を記号化して「神話」を合成しようとするのとは逆の方向を目指す作用です。E = mc2 をTシャツにプリントしている人を見たことがありますが、この数式をアインシュタイン神話の記号にしてしまうのではなく、記号 m の signifié とは何か、どのような意味をもつのか、そもそも質量とは何か、何に起源しているのかと問う、これが学術です。同様に、安全性を示すかのような数値を神話にするのではなく、その数値の意味するところを問い続ける、これが科学者の役割です。経済成長を表象していた統計データが、実はバイアスのかかった恣意的なものだったという事件も記憶に新しいところです(いや、もう忘れてしまった人の方が多いのかもしれません)。学術は、統計の正しい在り方を示し、粉飾を見破ることで、社会の信頼の拠り所となります。
詩人たちも同じように、表象に同化した風景、心象、知覚を問い直すことで、新たな感動を発見します。万葉集巻第二挽歌におさめられた歌:
有間皇子、自ら傷みて松が枝を結ぶ歌二首
磐代の濱松が枝を引き結び眞幸くあらばまた還り見む
家にあれば笥に盛るい飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る
この有名な短歌は、有間皇子(孝徳天皇の皇子)が、天智天皇や藤原鎌足の謀略によって反逆に誘導された末、捕えられて処刑の地へ向かう旅の途中で詠んだもの、呑気な旅行のエピソードではないことが詞書(題詞)から読み取れます。「椎の葉に飯を盛る」という非日常性は、「飯」や「椎の葉」の表象に同化した日常の風景を解体し、皇子の前にある「飯」や「椎の葉」は様々な情念を醸し出す記号になります。非日常性によって表象を引き裂く詩の作用が見事に実現されています。
このような「反神話作用」によって生み出される新鮮な感動を、ベルトルト・ブレヒトは「異化効果」と呼んで、彼の劇作の中で応用しています。ブレヒトが超克しようとしたのは、神話作用を濫用する演出家と、筋書きどおりの感動を消費する観客のもたれあいです。歌舞伎では「通」の観客が、予定どおり名場面が巡ってくるタイミングで「成田屋!」などと声をかけて舞台を盛り上げます。お笑いでも、芸人は決まった記号=ギャグを盛り込んだ芸を演じ、観客はお馴染みのギャグが披露されるのを期待しています。
常識を覆し、筋書きを超えた新たな展開を生むことが詩人、劇作家(前衛的な)、そして学術(真の)にたずさわる者が成すべきことです。神話を作ることとは反対の仕事です。「大きな物語」を尊敬や陶酔の対象にするのではなく、現前している個々の物事をリスペクトすることで、糸口がみつかります。科学神話や科学者神話のお定まりのストーリーに私たちは同化していないか、ときどき反省する必要があります。
「神話」というものの危うさについてみてきましたが、本題に戻って、リスペクトを同質性の次元へ引き戻し、具体的な人に差し向ける眼差しということについて考えてゆきましょう。理想的な社会の在り方とは、お互いをリスペクトすることで多様性を容認すること、意見の違いを認めながらも合意を形成できることです。どのような規模であれ、人の集合=社会が、メンバーの幸福を目的にしているなら、そこで起こるあらゆる相互関係はリスペクトを前提にすべきです。その場合の「合意」とは、意思の統一だとか、一致団結だとか、「神話」によって誘導される共感などとは違って、もっと緩やかで、多面的な解釈が可能で、もしかすると同床異夢でもよいかもしれません。合意の形成プロセスは、非効率をいとわず、参加者どうしが多様な意見にリスペクトをもち、自由な議論を交わすことが必要です。しかし残念なことに、このような理想を実現することは容易でありません。自分とは異なる意見を述べる者に罵詈雑言を浴びせかける、平気で嘘を言う、そういった人間ほど組織の中で権威を得る工作に長け、偏狭な自説を押し通す、そんな世界を見たり経験したりした人も多いのではないでしょうか。そこにあるのは「コミュニケーション」ではなく、狭量な戦略です。いろいろな「神話」が創作され、個々の現実への眼差しが遮断されてゆきます。
ユルゲン・ハーバマスは、コミュニケーション的行為と戦略的行為を峻別し、真のコミュニケーションによって合意を目指す社会の実現は、人類の「未完のプロジェクト」だとしています。達成することよりも、達成のための努力こそが重要なことが多々あります。平和、平等、自由・・・これらの理想を完全に達成することはできないのかもしれません。しかし、その未完のプロジェクトに参加し協力しあうことにこそ意味があるのではないでしょうか。そこには他者へのリスペクトがあるからです。
万葉集は、政争の犠牲になった有間皇子や大津皇子、名もなき防人、そして詠み人知らずの歌などを広く「言の葉」として収集した歌集です。立場や身分の隔てなく、いろいろな人々が感じ、考え、言葉にしたことを等しくリスペクトする、そういう文学の本質が実現されています。編者は、「大きな物語」や「神話」の構築を目指したのではなく、個々の素朴な心に眼差しを向けています。私たちが誇るこの文化遺産は、文化(科学・技術も含む)はいかにあるべきかを教えてくれているように思います。私たちの研究所も文化を育む場所でなくてはなりません。リスペクトを基調として、新たな発見に満ちた日々を送りたいものです。
本年が皆さんにとって幸多い歳となりますよう。