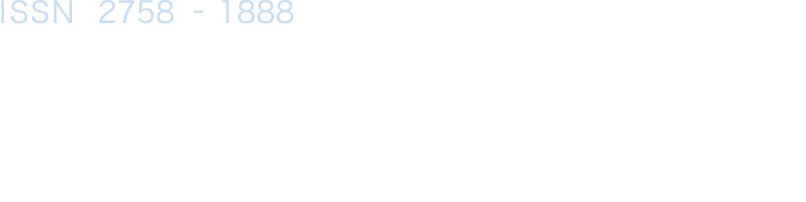明けましておめでとうございます。
所長として年頭所感を述べるのは今回が最後になります。これまで3回、「世界はこのようであってほしい」と思うことを書いて、新年の寿ぎとしてきました。今年はその締めくくりとして、「リベラル・アーツ liberal arts を身につけて、自由人として生きてほしい」という、私から皆さんへの期待(同時に、自分自身への課題)を述べようと思います。
ここでは、liberal arts を「自由に生きるための知の技法」と訳すことにします。artsを「知の技法」だと言う理由は、後で述べるように、「自由」ということは必ずしも単純ではない意味深長な内容を含むからです。自由の探求は、場合によっては苛烈な技術を用いる可能性があります。そうではなく、知によって自由を探求すべきだということが最も重要なポイントです。福沢諭吉が言った「一身独立して一国独立す」にも、この精神が基盤にあります。独立するとは、自由に生きる力を獲得するということです。そういう自由人の集団として初めて、一国の独立(そこまで大きく構える前に、まずは身近な組織のことを考えましょう)、すなわち他集団からの圧迫や干渉からの自由が成り立つ。これは「知」の力によって、はじめて可能だというのです。『学問のすすめ』は「リベラル・アーツのすすめ」に他ならないのです。
自由の尊さは、それを得ることの難しさと表裏一体の関係にあります。そのために、「自由」は哲学の根本的なテーマであり続けています。philosophy = sophia(知)をphilein(愛する)という生き方を貫くために、様々な次元で自由の意味が論じられてきました。最も根源的な次元での自由、すなわち「自由意志」ですら、決して自明ではなく、いろいろな考え方があります(ここで述べようとしているのは「右のリンゴを選ぶか、左のリンゴを選ぶかを決定する自由」といった幼稚な課題設定ではありません)。
カントは、自由意志とは道徳的な行動を選択できることだと述べています。しかし、人間は悪を選択する自由も持っています。それは、様々な欲望(生命的な原理)に係わる自然法則に身を委ねた選択であり、真の自由意志による選択とは言えない。カントにおける自由意志とは、生物的次元を超えた、真に人間的な次元における決定権を意味しています。そういう自由のための知の技法が、私が言いたいリベラル・アーツなのです。
一方、ニーチェは些か屈折した見方を示しています。私たちは自由に考えているのではなく、考えさせられている(考えた気にさせられている)、それを「我 Ich」に命じているのは非人称の主語たる「エス es」(英語における「it」)だと言うのです。この「エス」は、フロイトにおいては「無意識」を意味し、精神の中心部に広大な領域を占め、快感原則によって支配されている生物的な神経活動です(夢の残像という形でのみ、その活動の一部を知ることができます)。一方で、精神の外には、現実原則に従っている外界が広がっています。精神と外界の「境界」において、快感原則と現実原則の調整をはかろうと常に喘いでいる、薄く壊れやすい層こそが「意識」だというのです。ニーチェは、人の意識というものは自我に属する自由なものではなく、それが行う決定は、そもそも善悪の彼岸にあるものであって、征服欲ともいえる生命原理(力への意志)に従っていると理解すべきだと言います。こういう悲観的な理論は、「思想」として良いか悪いかという問題は別として、人間というものを理解するための一つの論点として、自然科学的な文脈でも、社会学的な文脈でも、認識にとめておく必要があります。
ニーチェは、自由という概念は「するもの」と「されるもの」によって構成されることを指摘し、そこに自由の暴力性を見ています。個人のレベルにおいては、「するもの」はエス(無意識の快感原則)、「されるもの」は自己の身体ということになりますが、さらに社会のレベルにおいても「するもの」「されるもの」があります。9.11テロを受けて実施された「不朽の自由作戦 Operation Enduring Freedom」「自由の番人作戦 Operation Freedom's Sentinel」のように、一方の自由は他方の死を意味することさえあります。こういった事態が世界に蔓延しています。暴力の応酬、恨みの循環から、どうすれば解脱できるのか、人間として正しい選択を与えるはずの「自由意志」はどうやって実現できるのか、何度も繰り返されるこの問いに、今また世界は直面しています。
人はみな、自分の枠(座標系)に当てはめて(投影して)世界を理解します。自分とは異なる次元でものを考えている人を理解することはできません。日常においても、話がかみ合わない、すれ違う、曲解されるなどの事態は、他人を自分の枠組み・物差しでしか理解できないという人間の根本的な特性に起因しています。世界を理解するための「知の枠組み」のことをフーコーは「エピステーメー épistémè」と呼びます。学問は、この知の枠組みの次元を高めるためにあります。想像力の涵養と言っても良いでしょう。一方、政治 politics は、エピステーメーに介入し、批判的な見方を縮退させ、1次元的な見方に民衆を誘導しようとします。「〇〇しかないのです。みなさん!」と叫んでいる「指導者」をよく見かけますが、こういう人達は、自分が信じる狭矮な世界観を超えた、多様な見方や考え方を本当に理解できていないようです(分かってやっているとすると、もっと質が悪い)。他者への眼差し respect をもつことができる人は、心の中に多様な他者を理解できる豊かな次元を持っています。これを涵養するために、文学や歴史、あるいは社会的な実践の場があります。物理学を極めた人が「プラズマの気持ちが分かる」と言ったりするのを聞くことがありますが、人の気持ちを理解するのは、もっと難しいように思います。
リベラル・アーツは、一身の独立のために獲得すべき知の技法です。その技法が「知的」であるためには、まず「世界を理解する」ということから事を始めなくてはなりません。世界とは実に興味深いものです。興味をもって見る、知ろうとする、そういう余裕をもつことができれば、つまり日常の中に埋没した経験的世界から時には身を引き離して、学ぶ時間をとる、考える時間をとることができれば、世界を理解する新しい次元が心の中に生まれてくると思います。新年という時の節目は、その良い機会になるのではないでしょうか。
本年が皆さんにとって幸多い歳となりますよう。