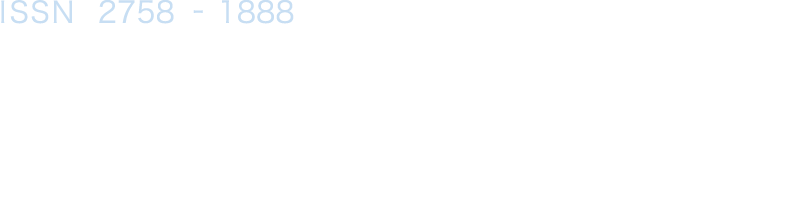|
|

|
所長を退任するにあたって、4年間の任期を振り返りつつ、これからの核融合研に期待することを述べようと思います。
世界の核融合研究は、70余年にわたる歴史を経て、いま大きな転換点を通過しようとしています。核融合研は「post-LHD」へ向けたパラダイム転換という形で、いち早く激動期に突入しました。このことは私たちにとって幸いだったと思っています。歴史的な評価は後世に委ねなくてはなりませんが、私たちが進もうとしている方向は、世界に一歩先んじた、また持続可能な発展を期待できる、賢明な選択だと信じています。
変化の兆しは、ロードマップ2020(文部科学省の研究環境基盤部会・学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会が3年ごとに策定する『学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想』2020年版)に提案されたLHD後継計画が選に漏れたことでした。これは、核融合科学の大型プロジェクトが、他分野の大型プロジェクトとの相対関係のなかで、高い優先度を認められなかったということを意味しています。他方で世界の動向に目を向けると、SDGsの課題でもあるカーボンニュートラル技術への期待が高まっており、2021年にはアメリカで核融合研究への民間投資が一挙に4000億円を超えました(これはアメリカ政府からの核融合研究予算の5倍近い値です)。この二つの事象は、「核融合 fusion」への期待という意味で、全く逆の方を向いています。
こうした二極の評価が併存する原因は、括弧付き「核融合」の多義性にあります。多義性を生みだしているのは、立場が違う人たちの理解の仕方と思惑です。言うまでもなく、私たちにとっての「核融合」は科学的・技術的な真実でなくてはなりません。研究開発にとって「期待」「夢」は、限界を克服し世界を拡大してゆく原動力ですが、それは自身の「期待」「夢」と整合したものでなくてはいけません。他者の「期待」「夢」を根拠にした営みは商人の生業であって、私たち職人は自身の「期待」「夢」に向けて「技」を根拠にして働くことで「もの」を生みだします。核融合研という研究者集団は、何を「期待」「夢」として活動しようとしているのか、それは広い社会(まずは他分野の研究者たち)の「期待」「夢」と整合し、共有できるものなのか、この問いが私たちの改革の起点でした。この答えがしっかりすれば、核融合研の将来計画は学術界で高い評価を得られるはずです。同時に、社会で浮遊している「期待」「夢」に対しても、科学的・技術的リアリティーへの投錨点を示すことができるはずです。
およそ1年の議論と熟考を経て導いた答えが「ユニットテーマ」です。これは、装置方式でアイデンティティーを主張し合う時代から、普遍的な科学・技術の言葉で分節化されたテーマを掲げ多様なイノベーションを競う時代へのパラダイム転換です。この画期的な転換点を所員の皆さんと共に生きた4年間は、私にとっても大きな挑戦でした。大変でしたが、充実した日々でした。改めて皆さんの努力に敬意を表し、協力に感謝します。
いろいろな職の任期が4年と定められているのは、文字通り「起承転結」という意味だと、つくづく実感しています。2021年度はパラダイム転換の起点でした。そこで策定したユニットテーマを承け、2022年度はユニット体制への移行の準備を進めました。2023年度はユニット体制への転換を成し遂げ、また新しいパラダイムの計画がロードマップ2023に掲載されました。そして2024年度が私にとっては4年間の挑戦の結びとなりました。核融合研に対する学術界および政府の信頼と期待は確実に高まってきたと感じています。しかし、まだ上向いてきたという段階であり、今後この新しいパラダイムの実効性を証明して行くという大きな仕事が核融合研の皆さんを待っています。ぜひ勇気と希望をもって進んでください。