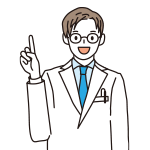かくゆう合のいま、これから
かくゆう合研究はどこまで進んでいるの?
プラズマを作る実験では、高い温度のプラズマを作ること、原子かく密度と閉じこめ時間のかけ算を大きくすることを目指しています。その最高記録を持っているのが、日本にあるトカマク型のJT-60という装置です。温度は5.2億度にもなります。閉じこめ時間も1秒をこえています。かくゆう合発電ができるプラズマに非常に近いのですが、持続時間が1分程度とまだ短いのです。この持続時間を長くすることがこれからの課題ですね。
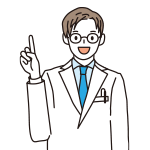
これからのかくゆう合実験
世界中の国々が協力して、かくゆう合実験ろ(ITER、イーター)をフランスに作っています。この実験ろでは重水素(記号:D)と三重水素(記号:T)を使って実際にかくゆう合反応(D-T反応)を起こします。そしてプラズマから10分程度の長い時間、エネルギーが発生することを確かめます。ITERの次は、発生するエネルギーを電気のかたちで取り出すことができる原型ろを作ります。これがかくゆう合発電所の第1号となります。2045年に完成するように設計や研究を行っています。
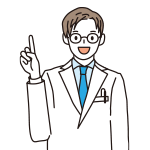
将来のかくゆう合発電ろ
近い将来にできるかくゆう合発電ろでは、重水素と三重水素を燃料としたかくゆう合反応を使います。このかくゆう合反応で中性子というりゅう子ができて、ものすごいスピードでプラズマから外に飛び出してきます。プラズマの周りにブランケットというかべを置いておくと、そこに中性子がぶつかって熱に変わります。この熱で水をふっとうさせて水蒸気に変え、タービン発電機を回すことで電気をつくることができます。水をふっとうさせるところからは、火力発電所や原子力発電所と同じしくみです。
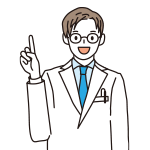
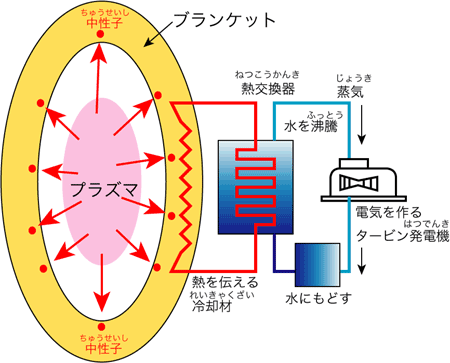
実現のために研究されていること:かくゆう合ろ設計
これまで作られた多くの装置のプラズマの性能を比べてみると、将来どのような大きさの装置を作ったらかくゆう合発電ろになるかが予想することができます。また他にもたくさんの計算をして、かくゆう合発電ろの大きさ、作る磁場の大きさなどを決めていきます。大きさが決まると今度は、色々な部品を設計します。そして発電所を作るためにかかるお金や作った電気の料金などを計算します。このような研究を「ろ設計研究」といいます。将来のことを考えながら、今しなければならない研究や実験のことを考えています。
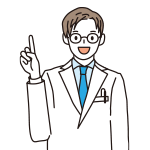
実現のために研究されていること:材料
かくゆう合を起こすプラズマからは、中性子という放射線が発生します。この中性子が金属やプラスチックに当たると、こわれやすくなります。だから中性子が当たってもこわれにくい材料を探しています。それから、中性子が当たった金属が放射線をだす性質に変わることがあります。だから放射線をだす性質に変わりにくい金属材料も探しています。
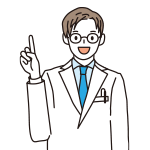
-269度まで冷やしたコイルはひずみませんか
-269度にすると金属は0.3パーセントだけ長さが短くなります。例えば10メートルのものは3センチメートル短くなることになります。冷えたところと冷えていないところの境目で長さが変わるので、スライドさせるなど、色々な工夫をしてこわれないようにしてあります。