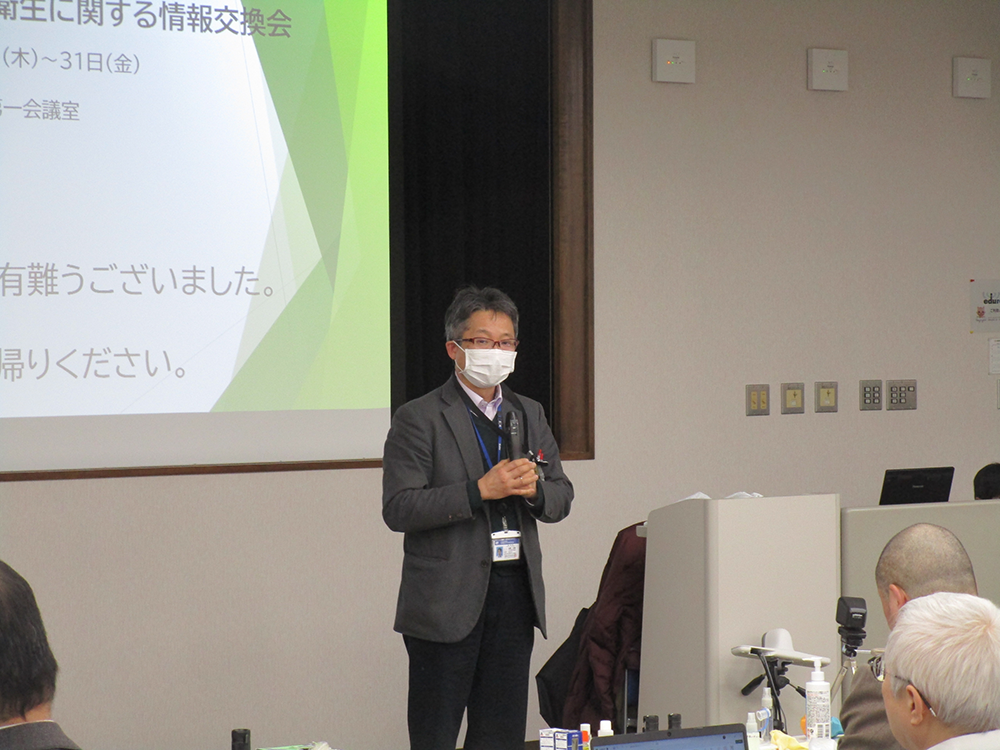2025.2.27
労働安全衛生に関する情報交換会(第20回)を開催
トピックス核融合科学研究所は令和7年1月30日と31日、「労働安全衛生に関する情報交換会」を開催しました。この会合は労働安全衛生法に基づく各機関の取組や活動状況及び課題等の情報交換を目的として、法人化後の平成16年度から毎年実施しており、今回で20回目となります。全国の大学、大学共同利用機関等21機関から安全衛生に関わる技術職員を中心に事務職員、研究教育職員、大学等環境安全協議会評議員、及び労働衛生コンサルタントを交えた約40名が参加しました。
開催にあたり長壁正樹安全衛生推進センター長からの「皆さんと再会できて何より。活発な議論を期待します。」との挨拶に続いて各機関から、大学における防火防災管理、安否確認訓練、廃棄物品管理、廃液管理、刈払機(草刈り機)の取扱基準、化学物質等の防護具管理、放射線教育等に関する10件の発表がありました。
化学物質等の防護具管理についての発表では、令和6年4月改定の「化学物質防護に対する不浸透性の保護具の使用義務」に関する実践的な対応例の紹介がありました。厚生労働省の運用マニュアルでは工場等での「作業者保護」の視点で高価で高耐性な保護手袋を事実上使い捨てにする運用が記されており、この経済的課題に対し安価で汎用の保護手袋を使い捨てにする運用例が示されました。工場等の生産現場に比べ大学等での実験室では扱う化学物質量が少ないことから「化学物質が保護手袋に付着したら浸透で皮膚に達する前に速やかに交換する」との発想です。ただし、これには保護手袋素材ごとの化学物質の浸透特性が現場で平易に確認できることが不可欠となりますが、身近にある油性ペンが活用できることが示されました。例えば、保護手袋に塗った油性ペンのインク色素が保護手袋素材の反対面に到達する時間が保護手袋を脱ぐ時間より十分長ければインクに含まれる有機溶剤に対して作業者は保護されることになります。発表中にこの実演がなされ参加者から高い関心が示されました。なお、「有機溶剤等は保護手袋を透過する。この事前教育が前提だ」との付け加えがありました。この手法は複数機関で試みられており管轄の労働基準監督署から「平易で実践的」と評価を得たとのことです。本会合のような機関間の交流活動を通じて、大学発の安全衛生基準への発展が期待されます。
大学構内からの排水管理についての発表では、大学移転当時の付近の下水道整備事情により自治体から法基準より厳しい排水管理基準を課せられたことに対して、誠実にその基準を守る努力を重ねつつ、近隣研究機関と合同での長年にわたる粘り強い自治体との折衝によりその基準改定を得たとの苦労話がありました。安全衛生活動における機関間連携の可能性が示された事例でありましょう。この「法基準より厳しい安全管理基準が求められる苦労とその後の展開」への取り組み事例は、抱える事案は異なりますが核融合研の職員にとり共感と何がしかの可能性や示唆を感じさせるものでした。
また、本会合に併せて研究所の大型ヘリカル装置(LHD)を含む実験施設の見学会が催されました。参加者からは大型ヘリカル装置(LHD)の建設や超電導コイル巻き線にまつわる苦労話に感嘆の声があがった他、見学経路上の消火設備、防災救護器具、安全標識、高圧ガスボンベ、高電圧機器の安全フェンス等に向けられた安全衛生担当者ならではの鋭い視線に同行した研究所の安全衛生スタッフは改めて気を引き締める場面もありました。
長壁センター長は、閉会の挨拶で「各機関の安全衛生活動を共有する良い機会です。今後ともこの会合を続けていきたい」と述べ、本会合を締めくくりました。末尾ですが本会合の開催にご協力いただきました皆様に感謝します。